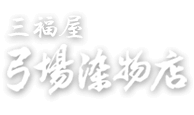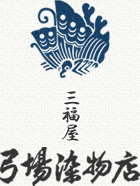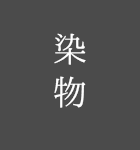当店では、「筒描染」といわれる、筒に入れた防染用の糊を絞り出しながら描く技法を主とし、型置き染・染料捺染などを行っています。
神社幕・寺幕・幟・夜具・油単・法被・風呂敷・のれんなど、生活に密着した物のほとんどがこのような染物です。
もち米の粉から作った糊を、筒から絞り出しながら文字や絵柄を描き、防染糊として使用します。
その起源には様々な説がありますが、糊を防染剤にした染色法は古くからあり、戦の旗指物がその起源と言われています。
現代では、そのダイナミックな構図や染め上がりから、大漁旗や神社幟などに使われています。
当店で使う糊は、職人がもち米の粉と糠で練った昔ながらの糊を使用しております。
布をお湯で洗い、不純物を取り除き、布を予め縮ませる。

下絵紅(したえべに)を使って、図柄、文字の輪郭線を描く。

筒袋(円錐形の筒)で糊を絞り出しながら、下絵に沿って描いていく。

刷毛を使って色を染めていく。(糊が防染剤となり、糊を置いた部分が白く残る。)その後乾燥させる。

染料を布に定着させるため熱処理を施す。

糊と、余分な染料を落とす。その後乾燥させる。

飾りなどをつけ、旗の形に仕立てる。
型置き染は、渋紙及び合成紙など水に強い紙に模様や文字を彫り
「型紙」をつくり、型の上から糊を置いて模様をつける技法です。
京友禅などの反物の柄なども、筒描やこの型置きが基本となっています。
当店に残る明治時代のものと思われる古い型紙には、故事を元にした多彩で繊細な柄が掘られています。こういった柄で、昔の職人はユーモアや粋な心を表現しました。


渋紙及び合成紙に手で絵柄を彫る。
筒置と同じく、お湯で布を縮ませ、不純物を取り除く。

出来上がりの形から型を置く位置などを決める。

型紙の上に枠を置き、布に均一に糊を置き、裏から水を打って糊を浸透させる。その後乾燥させる。

糊を浸透させ、糊際を整えて色むらを防ぐ。その後乾燥させる。
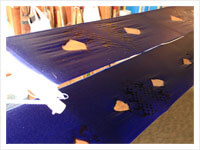
刷毛で均一に染料を引き、その後乾燥させる。
染料を布に定着させるための処理を施す。

水とお湯で余分な染料と糊を落とす。その後乾燥させる。

巾着など様々なものに仕立てる。